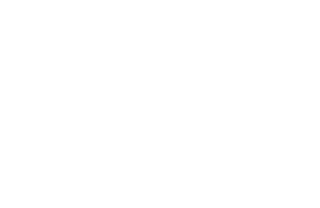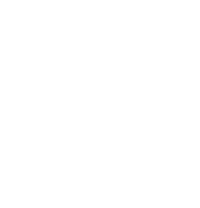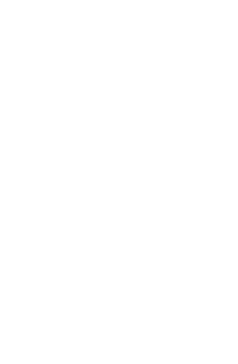お知らせ
[コラム]自己完結からアウトソーシング、さらにその先へ
2025.09.04
導入
かつて多くの自治体では、申請受付から審査・入力・発送、電話対応、システム管理に至るまで、すべての業務を自前で対応していました。責任の所在が明確で、緊急対応もしやすいといった利点はありましたが、定型業務に人手や時間が取られ、住民サービスや政策立案など本来注力すべき業務への支障も生じていました。
こうした背景から、「業務の一部を外に出す」アウトソーシングが進展しました。封入発送、申請入力、コールセンターなど定型業務を中心広まりましたが、多くは業務単位・自治体ごとに仕様が異なる「指示型アウトソーシング」で、業務全体の最適化や標準化には限界がありました。
従来型アウトソーシングの限界
近年では、人手不足の深刻化や業務の複雑化、多様化によって、従来のアウトソーシングでは十分対応できないケースが増えています。委託先が見つからない、マニュアル通りでは対応しきれない、スケールメリットが得られずコストが下がらないといった課題が表面化しています。これを無理に従来のやり方でアウトソーシングを行った結果、発注側の業務負担が軽減されないどころか、業務の可視化・標準化・調整など新たなマネジメント負荷が発生するケースも見受けられます。
業務改革としてのアウトソーシング
このような中、アウトソーシングを「業務改革の手段」として捉え直す動きが求められています。単に外注するのではなく、業務の見える化、再設計、共通仕様化などを通じて、業務プロセスそのものを再構築することが重要です。
もちろん、現場で長年培われた運用の見直しや共通仕様への調整など、変革には一定のハードルがあります。しかし長期的に持続可能な行政運営を目指すのであれば、可能な業務から段階的に着手し、自治体内外の信頼関係を築きながら新しいアウトソーシングを進めることが現実的なアプローチです。新しいアウトソーシングにより、業務の標準化やスケールメリットの活用が可能となり、コストの最適化や職員の業務負荷軽減といった具体的な効果が期待できます。
持続可能な行政運営のために
今後の自治体が目指すべきは、「発注する側」から「業務を設計し、標準化・共通化する側」への進化です。その先には、複数自治体が一体となり、業務を統合・一括委託する「共同アウトソーシング」のような形も視野に入れながら、持続可能な行政運営の実現を模索する必要があります。
参考文献:地方シンクタンク協議会. “NPM(New Public Management)の視点に基づく地方公共団体の効果的なアウトソーシング調査報告書”. 財団法人 関西情報・産業活性化センター. 2005-02. https://www.think-t.gr.jp/NPM/pdf/NPM_report_01.pdf, (参照2025-07-30).
本件に関するお問合せ先
株式会社エスプールグローカル 営業企画部
TEL:03-6859-6563
E-mail:glocal-contact@spool.co.jp